CI刷新から1年。
NOKに表れた「目に見える効果」から考える、
BtoB企業 ✕ クリエイティブの力
帰属意識(Belonging)を高める、ブランドアイデンティティのマイルストーン

1941年に創業し、自動車部品や精密機器業界で「知る人ぞ知る」日本発メーカーとして、独自のポジションを築いてきたNOK(エヌオーケー)グループ。
自動車のエンジンなどに使われる「オイルシール」で国内シェア70%、情報精密機器に用いる柔軟性のある回路基板「フレキシブルプリント基板(FPC)」で世界売上第3位と、確かな実績を上げ続けている。
「目立たない美徳」を貫いてきたNOKは、2024年4月、クリエイティブディレクターの佐藤可士和氏を起用し、コーポレートアイデンティティ(CI)を刷新。「目立つ」改革を選んだ。
企業としてのあり方を転換した決断から約1年が経過した今、NOKグループにはどんな変化が生まれているのか。“社会派クリエイティブ”を掲げDEIを軸にしたブランド施策を多数手掛ける辻愛沙子氏と、NOK代表取締役でグループCEOの鶴正雄氏との対談から紐解く。
「目立たない美徳」からの脱却
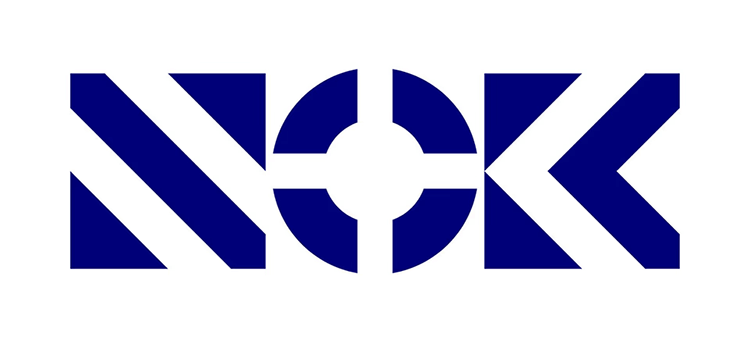
──辻さんは、NOKグループのCI刷新をどのように受け止められましたか?

辻:最初にNOKの新しいロゴを目にしたのは、移動中のタクシー広告でした。ボールドながら繊細さを感じるロゴが目に飛び込んできて、記憶に残っていて。
刷新の背景などを記事で拝読したところ、縁の下の力持ちのような「下支え」のイメージがある事業ドメインでありつつも、あえてそれを「中心領域」と標榜し、下から支えるのではなく中心から広げていくと再定義されていたのが印象的でした。これはクリエイティブで言う「見立て」の話です。働いていらっしゃる方々にとっても大きな意味を持つメッセージになりますし、日本のものづくりの誇りや精神性も表現されていると感じました。
──CI刷新に至った課題感を改めて教えてください。

鶴:いわゆる「JTC」※1と呼ばれる日本企業は、成長が止まっているといったネガティブな印象を持たれがちです。ただ、私はそれを疑問視しているんです。製品の品質に加えて「知覚品質」※2も高められれば、ポテンシャルを最大化でき、グローバルでの成長余地があるはずだと。
私が2021年に社長へ就任した時、主力の自動車産業はEV化や中国系メーカーの台頭など、グローバルでマーケットが大きく変化していました。そうすると、今までの部品メーカーとしての「目立たない美徳」が、むしろデメリットとして顕在化してきていたんです。
当社のものづくりの技術や営業力は圧倒的だと自負しながらも、それらを伝える力が足りない。NOKグループの存在感を社内外へ伝え、企業としての価値を上げていくようにシフトしないと、衰退していくのではという危機感がありました。
- JTC…Japanese Traditional Companyの頭文字。伝統的な日本企業を指し、古い価値観が残る企業を揶揄する際に使われることも多い。
- 知覚品質…消費者が代替品と比べた際に想起する品質や優位性。
──佐藤可士和氏との協働はどのように始まったのでしょうか。
鶴:最初からCIやロゴの相談をしたわけではありません。私たちの企業としての課題、つまり「いかに存在を社内外へ伝えて、企業としての価値を上げていくか」という本質的な悩みを話しました。
すると可士和さんはいきなりソリューションを出すのではなく、役員との対話や現場視察を重ね、私たちの情報を丁寧に咀嚼してくださいました。
その中で見えてきた大きな課題が2つあります。1つは創業以来、グループ企業がそれぞれ独自のCIでコミュニケーションを行っていた非効率さ。もう1つは、NOKが筆頭として92社のグループ会社を束ねる形ではありながらも、仲間としてはフラットであるべきという考え方をどう表現するか。そこから導き出されたのが、新たなCIだったのです。
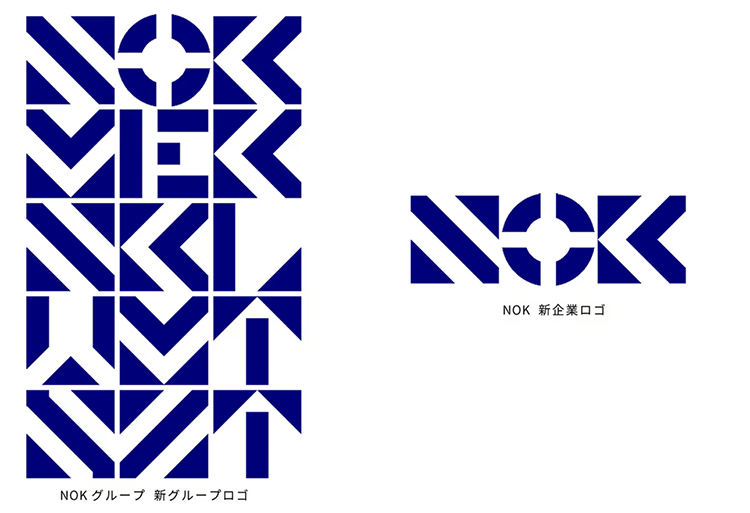
自分たちの行動と新CIの意味が重なり合ってきた

──CI刷新から1年、具体的にどのような変化がありましたか?
鶴:タウンホールミーティングを通じて、私から直接、従業員へ新CIの意図を説明し、質疑応答をしてきました。最近では「昔のロゴを見ると古く感じる」という声も聞きます。単なる視覚的な慣れではなく、自分たちの行動とCIの意味が重なり合ってきた証だと感じています。
辻:私もCIやブランドアイデンティティの刷新に携わる機会がありますが、そのときにいつも思うのは、外部の人間がいくら考え抜いたとしても、その会社の歴史への理解は実際に働いてこられた経営陣や従業員の方々には及ばないということです。
その自覚を持った上で、外からの目線だからこそすくい上げられる魅力や価値、そのブランドや企業の輪郭を可視化し、クライアントさんの中にある企業理解とすり合わせを行うのです。自分の魅力というものは、自分にとってはあたりまえなことすぎて、そこに価値があると気が付きにくいもの。人も企業も同様で、案外外からの目線があって初めて自分の中にある個性や魅力を知覚できたりするものです。
そんなプロセスを経て形作ったCI/VIが、クライアントさんの社内で少しづつ浸透してそこから対話が生まれたり、みなさん自身のものになっていったりする過程は、クリエイター冥利に尽きるなと思います。自分がつくったものが、自らの手を離れて呼吸をし、血肉になっていく感覚、といいますか。
上からではなく、中心から広げていくようなコミュニケーションをされる鶴さんのような方だからこそ、アウトプットがこの新CIになったのかもしれませんね。
鶴:ありがとうございます。タウンホールミーティングは海外拠点でも行い、CI刷新が「見た目だけの変化ではない」と従業員にも感じてもらえていると思います。最近では、海外拠点が自らNOKの価値観をベースに新しい事業を考え、人材交流や人事異動も生まれています。グローバル企業への変化を感じているところです。
企業アイデンティティを見つめる「Be」と「Do」
──新CIはグローバルでのビジネスにも良い影響を与えているのですね。
鶴:2024年7月からNOKグループは「グローバルマトリクス」と呼ぶ体制に移行しました。各事業はそれぞれ「縦軸」として持ちながら、繋がるべきコーポレートファンクションは「横軸」で展開していくという「掛け算の経営」を実践中です。
また、新CIを「佐藤可士和さんが手掛けた」という意味合いも、実は大きいです。名だたる企業を手掛けてきた可士和さんが、NOKが持っていた良さを言語化し、形にしてくださった。それは私も従業員も「自分たちは当たり前だと思っていたことが、実は特別だった」と再認識でき、自信につながっています。
──企業としての確かなアイデンティティを再定義するような機会でもあったと。

辻:自分たちのアイデンティティを考えるとき、日本文化的には「Do」の積み上げの先に「Be」がある、と捉えることが多いと思うんです。こういうことをやってきたから、自分たちはこういう会社である……というような積み上げの考え方ですね。しかし、グローバル企業の場合は逆で、往々にして先に「Be」、つまりはミッションやビジョン、パーパスを描いて、そこから「Do」をバックキャストしていく傾向が強い。
どちらがいい悪いというものではなく、単なるカルチャーの違いだと思うのですが、ときにデザイン性やビジョンのみが先行してしまうと、どうしても表層的な華やかさや言葉だけに留まってしまうことがあります。実体が伴わない変化では、本当の意味での進化は望めません。
そういう観点から見てみると、NOKには確かな歴史があって、そこで働く人たちが自らの手で積み重ねてきた技術や専門性がある。その積み上げてきた「Do」があるからこそ、自分たちがいかなる「Be」を言葉やビジュアルで可視化していこうか、という議論ができる。このバランスの良さは、数えるほどの企業しか持っていないことではないかと思います。
鶴:NOKグループは製品品質だけでなく、従業員も含めて、企業全体として品質を高めていく。「製品が良い、会社も良い、人も良い」と評価される企業になることを目指しています。
時代が変わっても「変わらない本質」とは何か
辻:私のもとにもDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン、多様性・公平性・包摂性)の文脈でブランディングのご相談をいただくことが多いのですが、やはり重要なのは、時代が変わっても変わらない本質があるということ。社会の多様性やその会社の固有性は時代のトレンドではなく、常に、すでに、そこにありつづけるものだからです。
その本質の“届け方”は、時代に合わせて調整が必要かもしれない。でも根幹は変わりません。むしろ、時代が揺れ動き自分たちもそれに揺らぎ迷いそうになったときにこそ立ち戻れるのが、アイデンティティであり、共通認識として持てる言語やデザインなのです。
DE&Iの領域では、最近はBelonging(帰属意識)の重要性も指摘されています。多様性は大切ですが、実はそれだけを追求すると、あらゆる企業が同じような比率に近づいて均質化するパラドックスに陥る。
だからこそ、Belongingとなり得る、自分たちの会社やブランドならではのアイデンティティを持つことが大切になります。そしてそれを掲げるだけでなく、経営体制や組織運営の方針も含めて実務に落とし込まれて有言実行されているNOKの取り組みは、確かな事例になるはずです。
鶴:私たちの変革は始まったばかりで、会社の歴史からすれば圧倒的に短い期間です。まだまだBelongingとまではいえないかもしれません。でも、これらの取り組みが当たり前になった人たちで社内が埋め尽くされれば、会社としての文化になります。新しく加わる人たちに対しても、やはり継続的に働きかけていかなくてはなりませんね。
タウンホールミーティングをやると、みんな共感してくれて「やりましょう!」となる。でも、自部署に戻ると、現実はそう簡単には変わらず元の気分・状態に戻ってしまう。
だからこそ、もう一度そこを引き上げるために、さまざまな施策を打っています。現場でミニ・タウンホールを開いたり、定期的にビデオメッセージを出して方向性をリマインドしたり。人間なので、どうしても意識は下がっていく。それをどう引き上げ続けるかが、人的資本経営の最も大切なところです。

辻:NOKは規模的にも大企業ですし、“個々の主語”よりもより大きな“組織としての主語”が強くなっていてもおかしくないと思うんです。それなのに、鶴さんは常に人的資本経営や社員を中心として物事を据えられている印象を受けました。
最近、批評家の宇野常寛さんの『庭の話』という本に触発されたのですが、現代社会では土や緑に触れるフィジカルな行為や実感がどんどん失われています。手触り感のないデジタル空間での仕事を積み重ねていくと、自分自身の手で何かを生み出したり、ケアしたり、ものごとを前に進めているという実感がどうしても持てづらい。自分のアイデンティティや、コミットしている仕事の達成感も感じづらくなってしまうと。だからこそ、『庭の話』ではフィジカルへの回帰を訴えかけていました。
NOKのものづくりへの向き合い方は、その意味でも示唆的です。確かな「もの」を作り出すこと、そして「中にいる人間」を、大切にし続ける姿勢が表れていますから。
鶴:やはり、ものづくりは綿々と受け継がれてきたNOKの企業文化でも誇れる部分ですし、結局ビジネスを動かしているのは「現場」なんです。NOKグループのメンバーは本当に自慢できる存在なんですよ。本質はいつも現場にあります。
辻:そう言える経営者は素晴らしいですし、きっとメンバーの方も嬉しいでしょうね。
鶴:今度は、ぜひ現場にも行ってみてほしいです。こうやって話をしているだけでは、NOKグループの本質まではきっと伝わりきらないでしょうから。